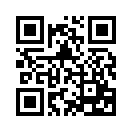2008年03月24日
第3回 NPOの知的戦略勉強会
第3回 NPOの知的戦略勉強会を3月21日に和歌山県NPOサポートセンターで開催しました。
前回に引き続き、NPOを巡るお金の話。
参加者でNPOを取り巻く課題をざっくばらんに出し合いましたところ、参加されている方の問題意識を(半ば強引に)まとめると、概ね、
(1) 理想と現実のギャップ
(2) 奉仕活動のバーンアウト
(3) お金の出所の不可視性
(4) 直間税と直接税の違い
の4つに集約できるかな、と。
つまり、
(1)は、NPOはかくあるべきだ、一種の社会変革性を持つことが必要だといいながら、実際はまだそこまでは全然至っていない
(2)は、奉仕活動はのめり込みすぎるとすべてをなげうってでも、的なバーンアウトをおこす可能性があること
(3)は、NPO法人の正式名称「特定非営利活動法人」の「非営利」の意味が正しく理解されておらず「非営利=非収益」という誤解がまだまだ多いことと、社会全体のお金の動きが見えにくくなっていることがひいては安易な行政批判や選挙の投票率の低下などといった重大なことを招いているのでは?ということ、
(4)は、税金のあり方を問いかけるもので、寄付税制の不備が指摘されるものの、税制が国によって異なるので、一概に日本でももっと寄付税制を!と呼びかけられない側面も認めなければならないのでは?という問題提起、
といった感じでした。
NPOを巡るお金の動きについては、NPO法人については直近3年間の事業報告・財政書類が閲覧できますから、この仕組みがもっと広がれば、NPO法人の財政の透明性は高まるだろう、そうすれば第三者評価もできるのでは、という期待の意見が出ました。
また、こういった地域に貢献するNPOを支える資金供給のあり方を市民参加で作り上げていくことは、地域での公的サービスを担うNPO活動を巡る資金の流れの透明性が増し、自分の出したお金がどこでどのように使われているかがより明確になります。そうすることで、みんなが地域の担い手に成りうるのではないか、という意見も出されました。
今後もこういった議論を深めていきたいということで一致。
次回の予定が固まりましたらまたご案内しますね。
前回に引き続き、NPOを巡るお金の話。
参加者でNPOを取り巻く課題をざっくばらんに出し合いましたところ、参加されている方の問題意識を(半ば強引に)まとめると、概ね、
(1) 理想と現実のギャップ
(2) 奉仕活動のバーンアウト
(3) お金の出所の不可視性
(4) 直間税と直接税の違い
の4つに集約できるかな、と。
つまり、
(1)は、NPOはかくあるべきだ、一種の社会変革性を持つことが必要だといいながら、実際はまだそこまでは全然至っていない
(2)は、奉仕活動はのめり込みすぎるとすべてをなげうってでも、的なバーンアウトをおこす可能性があること
(3)は、NPO法人の正式名称「特定非営利活動法人」の「非営利」の意味が正しく理解されておらず「非営利=非収益」という誤解がまだまだ多いことと、社会全体のお金の動きが見えにくくなっていることがひいては安易な行政批判や選挙の投票率の低下などといった重大なことを招いているのでは?ということ、
(4)は、税金のあり方を問いかけるもので、寄付税制の不備が指摘されるものの、税制が国によって異なるので、一概に日本でももっと寄付税制を!と呼びかけられない側面も認めなければならないのでは?という問題提起、
といった感じでした。
NPOを巡るお金の動きについては、NPO法人については直近3年間の事業報告・財政書類が閲覧できますから、この仕組みがもっと広がれば、NPO法人の財政の透明性は高まるだろう、そうすれば第三者評価もできるのでは、という期待の意見が出ました。
また、こういった地域に貢献するNPOを支える資金供給のあり方を市民参加で作り上げていくことは、地域での公的サービスを担うNPO活動を巡る資金の流れの透明性が増し、自分の出したお金がどこでどのように使われているかがより明確になります。そうすることで、みんなが地域の担い手に成りうるのではないか、という意見も出されました。
今後もこういった議論を深めていきたいということで一致。
次回の予定が固まりましたらまたご案内しますね。
2008年03月17日
ニッセイ財団 平成20年度高齢社会助成
ニッセイ財団では、「共に生きる地域コミュニティづくり」を基本テーマに、下記の「実践的研究助成」と「先駆的事業助成」の募集を行います。
助成募集分野と助成対象は以下の通りです。
I.実践的研究助成
5~8件程度、1件あたり今年10月から最長2年・200~250万円程度
1.認知症高齢者に関する予防からケアまでを探求する実践的研究
2. 高齢社会における地域福祉、まちづくりを探求する実践的研究
3. 高齢者の自立・自己実現・社会参加を探求する実践的研究
II.先駆的事業助成
2~3件程度、1件あたり今年10月から最長2年半・700万円以内
1. 認知症高齢者に関する予防からケアまでの総合的な先駆的事業
2. 高齢社会における地域福祉、まちづくりを目指す地域を基盤とした先駆的事業
3. 高齢者の自立・自己実現・社会参加を推進する地域社会システムづくりの先駆的事業
締め切り日は助成の種類によって異なります。
詳細はこちらをご覧下さい。募集要項、申請書ダウンロードもできます。
助成募集分野と助成対象は以下の通りです。
I.実践的研究助成
5~8件程度、1件あたり今年10月から最長2年・200~250万円程度
1.認知症高齢者に関する予防からケアまでを探求する実践的研究
2. 高齢社会における地域福祉、まちづくりを探求する実践的研究
3. 高齢者の自立・自己実現・社会参加を探求する実践的研究
II.先駆的事業助成
2~3件程度、1件あたり今年10月から最長2年半・700万円以内
1. 認知症高齢者に関する予防からケアまでの総合的な先駆的事業
2. 高齢社会における地域福祉、まちづくりを目指す地域を基盤とした先駆的事業
3. 高齢者の自立・自己実現・社会参加を推進する地域社会システムづくりの先駆的事業
締め切り日は助成の種類によって異なります。
詳細はこちらをご覧下さい。募集要項、申請書ダウンロードもできます。
2008年03月17日
JBC・CSR基金
----------------------------------
【JBC・CSR基金】2008年度の奨学金・助成金希望者募集のお知らせ
----------------------------------
JBC・CSR基金は、企業の収益を財源とした社会貢献活動の一環として
奨学金・助成金事業を行うNPOとして、2007年11月に設立しました。
現在、第1回の奨学金・助成金希望者の募集を受け付けております。
下記のサイトに、募集案内と応募登録フォームがありますので、ぜひ積極的
にご利用下さい。 → http://www.jbc-csr-fund.org/index.html
<JBC・CSR基金:奨学金プログラムの概要>
意欲と能力を持ちながら、経済的な問題などで勉学などの機会に恵まれない
青少年を応援します。高校生の時代に大いに学び、スポーツや文化活動など
にも積極的に参加することが、将来に向けての大きな財産となることを期待
しています。
対 象:高等学校(高等専門学校を含む)に在学あるいは入学予定の方
金 額:月額3万円(年間36万円)
支給期間:2008年度~正規の卒業年度
返 済:奨学金の半額については卒業後に分割又は一括返済を必要とし
ます。(半額分は返済不要です)
利 息:無利息
保 証 人:1名
募集人員:10名程度
募集期間:2008年3月1日~4月30日まで
詳細は、http://www.jbc-csr-fund.org/scholarship.htmlでご覧下さい。
<JBC・CSR基金:助成金プログラムの概要>
持続可能な社会の実現をめざして、環境保全活動や社会格差の是正などに取
り組む市民活動団体などを助成します。
自然環境や地域社会のあり方について将来的なビジョンを持ち、行政機関や
企業にはない柔軟な発想で、困難な課題に挑戦する「社会起業」的な取り組
みを応援します。
対 象:持続可能な社会をめざし、環境保全または社会格差の是正に
とりくむ市民グループなど
金 額:上限100万円
助成期間:原則として2008年6月からの1年間
募集予定数:5件(グループ)程度
募集期間:2008年3月1日~3月31日まで
詳細は、http://www.jbc-csr-fund.org/grant.htmlでご覧下さい。
【JBC・CSR基金】2008年度の奨学金・助成金希望者募集のお知らせ
----------------------------------
JBC・CSR基金は、企業の収益を財源とした社会貢献活動の一環として
奨学金・助成金事業を行うNPOとして、2007年11月に設立しました。
現在、第1回の奨学金・助成金希望者の募集を受け付けております。
下記のサイトに、募集案内と応募登録フォームがありますので、ぜひ積極的
にご利用下さい。 → http://www.jbc-csr-fund.org/index.html
<JBC・CSR基金:奨学金プログラムの概要>
意欲と能力を持ちながら、経済的な問題などで勉学などの機会に恵まれない
青少年を応援します。高校生の時代に大いに学び、スポーツや文化活動など
にも積極的に参加することが、将来に向けての大きな財産となることを期待
しています。
対 象:高等学校(高等専門学校を含む)に在学あるいは入学予定の方
金 額:月額3万円(年間36万円)
支給期間:2008年度~正規の卒業年度
返 済:奨学金の半額については卒業後に分割又は一括返済を必要とし
ます。(半額分は返済不要です)
利 息:無利息
保 証 人:1名
募集人員:10名程度
募集期間:2008年3月1日~4月30日まで
詳細は、http://www.jbc-csr-fund.org/scholarship.htmlでご覧下さい。
<JBC・CSR基金:助成金プログラムの概要>
持続可能な社会の実現をめざして、環境保全活動や社会格差の是正などに取
り組む市民活動団体などを助成します。
自然環境や地域社会のあり方について将来的なビジョンを持ち、行政機関や
企業にはない柔軟な発想で、困難な課題に挑戦する「社会起業」的な取り組
みを応援します。
対 象:持続可能な社会をめざし、環境保全または社会格差の是正に
とりくむ市民グループなど
金 額:上限100万円
助成期間:原則として2008年6月からの1年間
募集予定数:5件(グループ)程度
募集期間:2008年3月1日~3月31日まで
詳細は、http://www.jbc-csr-fund.org/grant.htmlでご覧下さい。
2008年03月14日
NPOの知的戦略勉強会 時間・場所の変更
2月に開催しましたNPOの知的戦略勉強会にて、次回を3月21日金曜日19時から、美園町の紀州まちづくりセンターで開催する予定とご案内しましたが、諸事情により、3月21日金曜日19時半から、和歌山ビッグ愛6階の和歌山県NPOサポートセンターで開催することとなりました。
なお、参加は今でも受付しております。
ブログ左側メニューの一番下の「メールする」からお申し込みください。
なお、参加は今でも受付しております。
ブログ左側メニューの一番下の「メールする」からお申し込みください。
2008年03月13日
和歌山市 市民公益活動団体と行政の協働指針策定
事業コーディネーターのしばです。
和歌山市では07年度、NPOやボランティア団体等の“市民公益活動団体”と行政との協働に関する指針の策定委員会を設置し、これまでに7回の議論を経て、指針の答申に至りました。
今後、和歌山市でも官民協働がより進むものと期待されます。
この関係の催しを2本ご紹介します。
答申記念シンポジウム 来週20日開催!
日時 2008年3月20日(木・春分の日)14:00~16:30
場所 和歌山市勤労者総合センター 6階文化ホール
定員 50名(事前申し込みが必要です)
内容
・基調講演 堀内 秀雄 氏(指針策定委員長・和歌山大学教授)
・指針答申
・記念公園 播磨 靖夫 氏(日本NPOセンター代表理事)
・パネルディスカッション
パネリスト
大橋 建一・和歌山市長
島 久美子(和歌山県NPOサポートセンター長、わかやまNPOセンター副理事長)
真砂 美香 氏(わかやまメディアリテラシー研究会代表)
播磨 靖夫 氏
コーディネーター
有井 安仁(和歌山市NPO・ボランティアネットワーク協議会会長、わかやまNPOセンター副理事長)
・問い合わせ・申し込み
和歌山市NPOボランティア推進課(TEL 073-402-1213、FAX 073-402-1214)
協働ウォッチング in わかやま ~協働環境調査報告会~
昨年度(つまり今回の答申が出る前)の和歌山市における官民協働の状況についての分析結果をご報告いただき、今回の答申を受けて、どのように官民協働を進めていけばいいか探ります。
日時 2008年3月22日(土) 13:30~17:00
場所 和歌山市NPOボランティアサロン
内容
・解説「第3回協働環境調査から見えてきたこと」
川北 秀人氏(IIHOE代表)、芝原 宏美氏(IIHOE上級研究員)
・日本財団公益コミュニティサイト「CANPAN」のご紹介
・事例紹介「和歌山市における協働の指針策定に関して」
・意見交換「よりよい協働のためにすべきこと・できること」
定員 50名(事前のお申し込みをお願いします)
費用 1,000円(資料代)
報告会参加者の方に限り、「協働環境調査」報告書を3,150円(税込・通常価格4,200円)で購入可能です。
問い合わせ・申し込み 和歌山県NPOサポートセンター(TEL 073-435-5424、FAX
073-435-5425)
和歌山市では07年度、NPOやボランティア団体等の“市民公益活動団体”と行政との協働に関する指針の策定委員会を設置し、これまでに7回の議論を経て、指針の答申に至りました。
今後、和歌山市でも官民協働がより進むものと期待されます。
この関係の催しを2本ご紹介します。
答申記念シンポジウム 来週20日開催!
日時 2008年3月20日(木・春分の日)14:00~16:30
場所 和歌山市勤労者総合センター 6階文化ホール
定員 50名(事前申し込みが必要です)
内容
・基調講演 堀内 秀雄 氏(指針策定委員長・和歌山大学教授)
・指針答申
・記念公園 播磨 靖夫 氏(日本NPOセンター代表理事)
・パネルディスカッション
パネリスト
大橋 建一・和歌山市長
島 久美子(和歌山県NPOサポートセンター長、わかやまNPOセンター副理事長)
真砂 美香 氏(わかやまメディアリテラシー研究会代表)
播磨 靖夫 氏
コーディネーター
有井 安仁(和歌山市NPO・ボランティアネットワーク協議会会長、わかやまNPOセンター副理事長)
・問い合わせ・申し込み
和歌山市NPOボランティア推進課(TEL 073-402-1213、FAX 073-402-1214)
協働ウォッチング in わかやま ~協働環境調査報告会~
昨年度(つまり今回の答申が出る前)の和歌山市における官民協働の状況についての分析結果をご報告いただき、今回の答申を受けて、どのように官民協働を進めていけばいいか探ります。
日時 2008年3月22日(土) 13:30~17:00
場所 和歌山市NPOボランティアサロン
内容
・解説「第3回協働環境調査から見えてきたこと」
川北 秀人氏(IIHOE代表)、芝原 宏美氏(IIHOE上級研究員)
・日本財団公益コミュニティサイト「CANPAN」のご紹介
・事例紹介「和歌山市における協働の指針策定に関して」
・意見交換「よりよい協働のためにすべきこと・できること」
定員 50名(事前のお申し込みをお願いします)
費用 1,000円(資料代)
報告会参加者の方に限り、「協働環境調査」報告書を3,150円(税込・通常価格4,200円)で購入可能です。
問い合わせ・申し込み 和歌山県NPOサポートセンター(TEL 073-435-5424、FAX
073-435-5425)
2008年03月11日
「高齢者等介護団体向け」リユースPC寄贈プログラム
東京のNPO法人イーパーツでは、高齢者等の介護を中心に活動を行っている非営利団体の情報化支援を目的とした<高齢者介護団体向け:リユースPC寄贈プログラム>を行なっています。
ケアマネジメント・広報・経理などでPCが不足している、 PC増設によって活動が活性化するとお考えの団体様は、この機会に申請をご検討いただければ幸いです。
【公募期限】 4月10日(当日消印有効)
【寄贈 PC】 TOSHIBA Satellite1850 SA120C/4(合計30台)
PentiumIII、1.2GHz、メモリ 256MB、ハードディスク20GB
CD-ROMドライブ付属(DVDドライブは付属しません)
【寄贈ソフト】 WindowsXp、OfficeXp
【対象の団体】高齢者等の介護団体様からご申請いただき、選考会にて寄贈を決定させていただきます。
【申込み方法・詳細】下記URLをご覧ください
http://www.eparts-jp.org/act/publicoffer/index.html
ケアマネジメント・広報・経理などでPCが不足している、 PC増設によって活動が活性化するとお考えの団体様は、この機会に申請をご検討いただければ幸いです。
【公募期限】 4月10日(当日消印有効)
【寄贈 PC】 TOSHIBA Satellite1850 SA120C/4(合計30台)
PentiumIII、1.2GHz、メモリ 256MB、ハードディスク20GB
CD-ROMドライブ付属(DVDドライブは付属しません)
【寄贈ソフト】 WindowsXp、OfficeXp
【対象の団体】高齢者等の介護団体様からご申請いただき、選考会にて寄贈を決定させていただきます。
【申込み方法・詳細】下記URLをご覧ください
http://www.eparts-jp.org/act/publicoffer/index.html
2008年03月10日
日高NPO交流会を開催しました
事業コーディネーターのしばです。
和歌山県NPOサポートセンターでは、日高地区のNPOのみなさんによる交流会を7日金曜日に開催しました。
昨年、日高振興局で開催した行政とNPOの交流会の場で、NPOのみなさんから「NPO同士が話し合える場がもっとあれば・・・」というご意見を頂戴しまして、その声を反映させる形で開催したものです。
平日の夜ということもあって、参加された方は少なかったのですが、はじめはやや静かだった会場も時間が経つにつれて同士活発な意見交流へと発展。
地域の課題を解決することを第一義とするNPOのみなさんですから、地域で様々な悩み事や困りごと、矛盾と感じられていることはよく似ているんですよね。逆にその矛盾をなんとかしたい、と思うからNPOを立ち上げて地道に活動をされてこられてきたわけでもあります。
わたしが入らせていただいたグループで、他地域の事例をご紹介しましたら、ぜひそこに行ってみたい!とおっしゃられた方がいらっしゃいまして、簡単な地図を書いて差し上げました。また、わかやまCBウイークのワークショップ(http://cbwaka.ikora.tv/e105396.html)で発表された「ビジネスモデル」、これって御坊であれば割と簡単に実現できるのでは?ということで、NPO同士の結びつきを強めNPO同士の協働を実現することによる新たな可能性もみえてきました。
御坊市自体は和歌山県でいちばん人口が少ない市ですが、それだからこそ、地域の課題がみんなの課題として広く共有されているように感じました。こういう地域課題を語り合って、自分たちのNPOでできること、ほかのNPOとの連携でできること、模索すればたくさん出てくるのではないかな?と思えた週末の夜でありました。
和歌山県NPOサポートセンターでは、日高地区のNPOのみなさんによる交流会を7日金曜日に開催しました。
昨年、日高振興局で開催した行政とNPOの交流会の場で、NPOのみなさんから「NPO同士が話し合える場がもっとあれば・・・」というご意見を頂戴しまして、その声を反映させる形で開催したものです。
平日の夜ということもあって、参加された方は少なかったのですが、はじめはやや静かだった会場も時間が経つにつれて同士活発な意見交流へと発展。
地域の課題を解決することを第一義とするNPOのみなさんですから、地域で様々な悩み事や困りごと、矛盾と感じられていることはよく似ているんですよね。逆にその矛盾をなんとかしたい、と思うからNPOを立ち上げて地道に活動をされてこられてきたわけでもあります。
わたしが入らせていただいたグループで、他地域の事例をご紹介しましたら、ぜひそこに行ってみたい!とおっしゃられた方がいらっしゃいまして、簡単な地図を書いて差し上げました。また、わかやまCBウイークのワークショップ(http://cbwaka.ikora.tv/e105396.html)で発表された「ビジネスモデル」、これって御坊であれば割と簡単に実現できるのでは?ということで、NPO同士の結びつきを強めNPO同士の協働を実現することによる新たな可能性もみえてきました。
御坊市自体は和歌山県でいちばん人口が少ない市ですが、それだからこそ、地域の課題がみんなの課題として広く共有されているように感じました。こういう地域課題を語り合って、自分たちのNPOでできること、ほかのNPOとの連携でできること、模索すればたくさん出てくるのではないかな?と思えた週末の夜でありました。
Posted by 事務局 at
17:44
│主催事業・イベント情報
2008年03月03日
NPO法人vs新公益法人か
事業コーディネーターのしばです。
2月29日にポストしました「NPOの知的戦略勉強会」の際に、偶然、新しい公益法人制度の話が出まして、いろいろ資料を探しておりました。
そうしましたら、和歌山県総務学事課の「公益法人制度改革について」に内閣府の資料へのリンクと共に結構くわしく掲載されていましたので、一通りながめてみました。
直接、NPO法人の制度に関係してきそうなところもみつかりましたので、ご紹介します。
---
この新しい公益法人制度は、社団法人と財団法人に適用されるもので、今年12月1日に施行されます。
大きく変わる点として、これまで行政の許認可制だった社団・財団法人が、法律に基づく要件を満たしていれば登記だけで設立できるようになります(一般社団法人・一般財団法人)。そのなかで、第三者機関の認定を受けた法人が公益社団法人・公益財団法人として、現行の社団法人・財団法人とほぼ同じ体制・税制で活動できるようになります。逆に、一般社団・財団は、共益的活動を行う場合の会費等を除くと原則課税となる、という方向で議論が進められているようです。
現行の社団・財団法人は、5年間の猶予期間の間に、一般または公益の社団・財団法人への移行手続きを踏むことになります。
---
この公益法人制度改革の概要のなかにNPO法人制度にひっかかる点がいくつかありましたので、ご紹介します。
まず、新しい公益法人制度がおこなう「公益目的事業」が次の23種類に分けられています(出典:公益法人制度改革の概要/行政改革推進本部事務局)。クリックで拡大表示します。
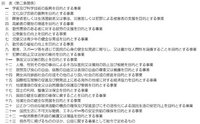
NPO法人の活動分野はNPO法により17分野にわけられていますが、それよりも6分野多くなっています。同じ公益的活動をおこなう公益法人なのですが、この違いをどう捉えるかが課題となりそうです。
二つ目に「公益法人制度改革の概要」のQ&Aコーナーに以下の文面があります。
Q. 公益目的支出計画が完了していないのですが、解散することになりました。清算後の残余財産はどのように処分したらよいのでしょうか。
A. 公益目的支出計画が完了しない時点で解散した場合は、その定款の定めの如何にかかわらず、解散した法人が公益目的支出計画に従い公益の目的に支出すべき残額があるときは、その残額に相当する残余財産については、行政庁の承認を得て、当該法人の目的に類似する目的を有する公益法人認定法に基づく公益法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人等か、国、地方公共団体に帰属させなければなりません。
今のNPO法では、残余財産の帰属先は、ほかのNPO法人、国・地方公共団体、財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人に限られています。しかし、財団法人、社団法人自体がこの公益法人制度改革でなくなりますし、NPO法制定後に新たな公益的な法人もできています。
この残余財産の帰属先はおそらく変更となるでしょうし、NPO法の見直し論議のなかでも取り上げられていました。
三つ目に、一般社団・一般財団法人は貸借対照表などの財務諸表を公告しなければなりません(公益社団・財団の場合はどうなのかは資料に記述はありませんでしたが、公益法人認定時には損益計算書等の提出が義務づけられると思われますので、それに代わるか、一般同様公告をする必要があるのは間違いなさそうです)。この公告の方法は「インターネットでも可能」となっています。
現在NPO法人の公告は民法の規定により、官報への掲載が義務づけられています。それも3回必要です(3回の掲載で9~10万円かかるといわれています)。
NPO法人が公告を必要とするのは多くが解散による債務者への通知ですので、一般社団・財団の財務諸表の公告とはわけが違うのですが、とはいえ、費用負担が大きいことや、最近は電磁的媒体による総会招集通知を可能に、なんて議論がでるくらいですから、公告の方法が変わる可能性が高そうです。
公益法人改革にともなう税制がどうなるかはまだはっきりとはしていませんので、NPO法人の税制がどうなるかはわかりませんが、NPO法人の制度自体には何らかの影響が出ることは間違いなさそうです。また、一般社団・財団法人は公証人による定款の承認は必要ですが、登記のみで設立できることから、認証が必要なNPO法人との違いがどうなるか、余計にあやふやになりそうです。
税制がどうなるかわからないという前提ではありますが、日本NPOセンターの山岡副代表理事がひとまずの整理をされていますので、ご関心のある方はそちらもご覧いただければ幸いです。
この件については、わたしたちNPOを支援する立場としてもしっかり勉強していきます。
2月29日にポストしました「NPOの知的戦略勉強会」の際に、偶然、新しい公益法人制度の話が出まして、いろいろ資料を探しておりました。
そうしましたら、和歌山県総務学事課の「公益法人制度改革について」に内閣府の資料へのリンクと共に結構くわしく掲載されていましたので、一通りながめてみました。
直接、NPO法人の制度に関係してきそうなところもみつかりましたので、ご紹介します。
---
この新しい公益法人制度は、社団法人と財団法人に適用されるもので、今年12月1日に施行されます。
大きく変わる点として、これまで行政の許認可制だった社団・財団法人が、法律に基づく要件を満たしていれば登記だけで設立できるようになります(一般社団法人・一般財団法人)。そのなかで、第三者機関の認定を受けた法人が公益社団法人・公益財団法人として、現行の社団法人・財団法人とほぼ同じ体制・税制で活動できるようになります。逆に、一般社団・財団は、共益的活動を行う場合の会費等を除くと原則課税となる、という方向で議論が進められているようです。
現行の社団・財団法人は、5年間の猶予期間の間に、一般または公益の社団・財団法人への移行手続きを踏むことになります。
---
この公益法人制度改革の概要のなかにNPO法人制度にひっかかる点がいくつかありましたので、ご紹介します。
まず、新しい公益法人制度がおこなう「公益目的事業」が次の23種類に分けられています(出典:公益法人制度改革の概要/行政改革推進本部事務局)。クリックで拡大表示します。
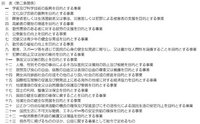
NPO法人の活動分野はNPO法により17分野にわけられていますが、それよりも6分野多くなっています。同じ公益的活動をおこなう公益法人なのですが、この違いをどう捉えるかが課題となりそうです。
二つ目に「公益法人制度改革の概要」のQ&Aコーナーに以下の文面があります。
Q. 公益目的支出計画が完了していないのですが、解散することになりました。清算後の残余財産はどのように処分したらよいのでしょうか。
A. 公益目的支出計画が完了しない時点で解散した場合は、その定款の定めの如何にかかわらず、解散した法人が公益目的支出計画に従い公益の目的に支出すべき残額があるときは、その残額に相当する残余財産については、行政庁の承認を得て、当該法人の目的に類似する目的を有する公益法人認定法に基づく公益法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人等か、国、地方公共団体に帰属させなければなりません。
今のNPO法では、残余財産の帰属先は、ほかのNPO法人、国・地方公共団体、財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人に限られています。しかし、財団法人、社団法人自体がこの公益法人制度改革でなくなりますし、NPO法制定後に新たな公益的な法人もできています。
この残余財産の帰属先はおそらく変更となるでしょうし、NPO法の見直し論議のなかでも取り上げられていました。
三つ目に、一般社団・一般財団法人は貸借対照表などの財務諸表を公告しなければなりません(公益社団・財団の場合はどうなのかは資料に記述はありませんでしたが、公益法人認定時には損益計算書等の提出が義務づけられると思われますので、それに代わるか、一般同様公告をする必要があるのは間違いなさそうです)。この公告の方法は「インターネットでも可能」となっています。
現在NPO法人の公告は民法の規定により、官報への掲載が義務づけられています。それも3回必要です(3回の掲載で9~10万円かかるといわれています)。
NPO法人が公告を必要とするのは多くが解散による債務者への通知ですので、一般社団・財団の財務諸表の公告とはわけが違うのですが、とはいえ、費用負担が大きいことや、最近は電磁的媒体による総会招集通知を可能に、なんて議論がでるくらいですから、公告の方法が変わる可能性が高そうです。
公益法人改革にともなう税制がどうなるかはまだはっきりとはしていませんので、NPO法人の税制がどうなるかはわかりませんが、NPO法人の制度自体には何らかの影響が出ることは間違いなさそうです。また、一般社団・財団法人は公証人による定款の承認は必要ですが、登記のみで設立できることから、認証が必要なNPO法人との違いがどうなるか、余計にあやふやになりそうです。
税制がどうなるかわからないという前提ではありますが、日本NPOセンターの山岡副代表理事がひとまずの整理をされていますので、ご関心のある方はそちらもご覧いただければ幸いです。
この件については、わたしたちNPOを支援する立場としてもしっかり勉強していきます。